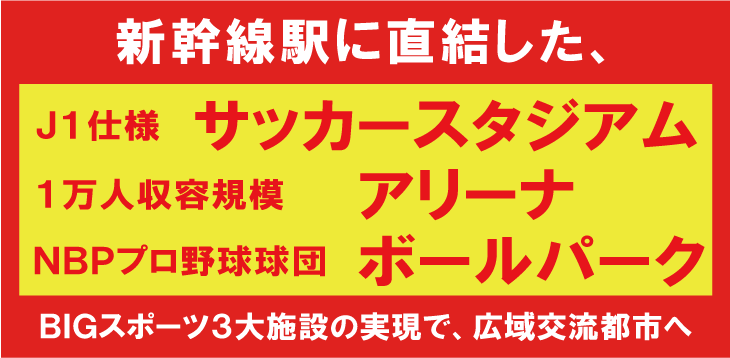 |
 |
|
<検討したい項目>
・高岡スポーツコアにJ1仕様の新サッカースタジアムを整備
・開閉屋根付サッカースタジアム(3万人収容規模)を目指す
↓ 開閉屋根を持つ『スタジアム神戸』
|
 |
<新サッカースタジアムの必要性>
いま全国では、サッカー専用スタジアムの建設や構想が増えている。サッカー専用スタジアムは、プロサッカーのプレイを、ちゃんと観客が楽しいと思ってもらうことが目的だ。観戦がつまらないと、観客はもう一度、試合を見に行こうとはならない。
富山県でJリーグが開催できるのは、富山県陸上競技場(2万5千人収容)だけだが、富山県陸上競技場は名称からも陸上を目的としており、球技競技には適していない。更に、フィールド・トラックを広くした為、スタンドからフィールド(ピッチ)までが遠く、スタンド自体もなだらかな為、サッカー観戦としては評判が良くない。そこで、Jリーグチーム『カターレ富山』に相応しい、本格的なサッカー専用スタジアムが必要不可欠だ。Jリーグでは、スタジアム基準がある。J1仕様のスタジアムは、観客席が1万5千人以上(椅子席1万席以上、メインスタンドに要屋根設置、芝生席は含めない)とされている。J2仕様のスタジアムは、観客席が1万人以上(椅子席8千席以上、メインスタンドに要屋根設置、芝生席は含めない)とされている。
お隣りの長野県松本市には、松本山雅のホームスタジアム「アルフィン」(建設費60億円)がある。2万人収容の観客席をはじめ、大型ビジョンや独立シートなどJ1基準をクリアしている。そして、何といってもプレイするフィールド(ピッチ)と観客席が非常に近く設計されており、試合観戦が楽しいスタジアムとなっているのだ。また長野市には、AC長野パルセイロのホームスタジアム「南長野運動公園総合球技場」がある。事業費80億円を掛けて大規模改修を行い、1万5千人収容の観客席と観客席4面に屋根を持つスタジアムとなった。J1仕様のスタジアムが、長野県には2つもあるが、いずれも長野県が整備を行っている。金沢市でも、建設費79億円をかけてサッカー専用スタジアム『GOGOカレースタジアム』を整備した。観客席は1万人収容だが、将来1万5千人に拡張できるように建設前から設計されている。しかも、観客席の最前列からピッチまでが、最短7メートルとサッカー観戦が楽しめる仕様となっている。
イギリスのプレミアやイタリアのセリアAで使われているフットボール(サッカー)スタジアムは、フィールド(ピッチ)と観客席が非常に近く、迫力あるプレイが楽しめる。富山県で新しいサッカースタジアムを建設する場合は、欧州のスタジアムを参考にする必要があるだろう。また、札幌ドーム(建設費422億円、4万人収容)・大分ドーム(建設費250億円、4万人収容)・豊田スタジアム(建設費340億円、4万5千人収容)・神戸スタジアム(建設費230億円、3万4千人収容)など、J1リーグが行える開閉式の屋根付フットボールスタジアムも参考に、屋根付きスタジアム建設(2万人収容規模)の構想化を期待したい。全国的にも、Jリーグが開催できる開閉式スタジアムが5箇所に広がっており、野球が開催できるドームスタジアム、札幌(サッカー兼用)・東京・西武・名古屋・大阪・福岡の6箇所に比べても、引けを取らなくなってきた。欧州のスタジアムでも、オランダにあるAFCアヤックスのホームスタジアム「アムステルダム・アレナ」は、透明膜で出来た開閉式スタジアムで、周辺には鉄道駅や商業施設も整備され、試合観戦を楽しめる魅力的なスタジアムとなっている。
富山経済同友会でも、以前に富山市の城址公園に1万5千人収容の多機能複合型サッカー専用スタジアム構想を打ち出したことがあった。可動屋根付きで建設費は125億円規模を想定したもので、極めて魅力的な構想ではあったが、残念ながら話は立ち消えとなった。
現在は、富山県サッカー協会で新サッカースタジアム建設に向けた取り組みが行われている。富山駅から歩いて行ける『まちなかスタジアム』として、ショッピングセンターやスパ施設を併設したヨーロッパ型のスタジアムを想定している。日本サッカー協会が支援することや、建設に向けてはスポーツ施設整備に実績がある日本総合研究所がサポートするという。ただ、想定している構想は大規模で、実現するには多額の建設費が見込まれ、推定でも500億円を超える規模になるだろう。建設費の多くは、富山県・富山市などが負担することになることから、実現までには紆余曲折が予想される。
↓ クリックで拡大表示します
|

<『高岡スポーツコア』に、 J1仕様のスタジアム実現を!>
そこで考えたいのが、高岡スポーツコアに本格的なJ1仕様のスタジアムを整備することだ。富山県サッカー協会では、いち早くスポーツコアでの整備案は排除された。しかし、高岡スポーツコアであれば新高岡駅に近いため、Jリーグの試合を開催できれば広域からの誘客も可能となり、新高岡駅の利用者確保にも役立つことが期待できる。新高岡駅を出ると、正面にサッカースタジアムを臨むことができるため、観戦意欲を高められる効果もあるだろう。
また、城端線がJR西日本からあいの風とやま鉄道に移管されることが決まったことで、新高岡駅から富山駅への運行本数増加が期待できるメリットもある。新高岡駅の隣り駅『二塚駅』には、待避線が複数あるため、試合終了後にあわせて臨時列車を運行することも可能だ。JR西日本から運営を引き継ぐあいの風とやま鉄道にとっても、この場所に新スタジアムがある意義は大きいと言える。
現在、高岡スポーツコアには、サッカーラグビー場がある。これをJリーグ仕様のサッカー専用スタジアムに改修したい。具体案としては、1万5千人〜2万人収容規模で、できれば可動式の開閉屋根も備えたい。まずは、4面の観客スタンドに屋根を設置して、あとから開閉屋根を追加することも考えられる。建設費については、開閉屋根なしの観客スタンドで50億円を想定。後付けで簡易的な開閉屋根の設置を目指したい。建設費を抑えるために、蛇腹式で薄膜仕様の開閉屋根として、雨天時のみに屋根を閉じる仕様とする。この仕様であれば、追加建設費は50億円規模で実現ができるだろう。
サッカー専用スタジアムの構想実現には、高岡スポーツコアのエリアを拡張する必要もある。新高岡駅とスポーツコアの間には、開発可能な広大なエリアが存在する。ここをスポーツコアの拡張エリアとしたい。スタジアムに隣接して、ショッピングセンター、温泉スパ、都市型ホテル、スポーツ系アミューズメント施設を併設することで、日頃から市民が集える場所を目指したい。また、拡張エリアには、計画が凍結されている新体育館を設けたい。現在の構想では、3千人収容の体育館だが、富山県・石川県で最大の1万人収容が可能なアリーナとする必要がある。これによって、高岡スポーツコアは、日本海最大級のスポーツメッカとなることができるだろう。実現すれば、広域からの集客が期待できる。
さらに、期待したいのはイオングループの参画だ。スポーツコアの隣接地にはイオンモール高岡がある。その集客力は、富山県全体に及ぶ。新スタジアムにイオンが参画してもらえれば、実現性が高まるだろう。イオンでは、秋田市でサッカースタジアムの建設を行政とともに計画した経緯がある。建設費の1/3をイオンが負担して運営も担う計画だったが、秋田市と秋田県の間で調整が難航して、計画は頓挫した。高岡でイオンを動かすには、チャンスかもしれない。また、toto助成金などを活用も必要だろう。民設民営のスタジアムとすることができれば、行政負担は軽減することができる。
スポーツコアのサッカー専用スタジアム整備として参考にしたいのが、ガンバ大阪のホームとしている『市立吹田サッカースタジアム』だ。4万人収容で、4面の観客スタンドには屋根も設置されている。その建設費が140億円という破格の安さで、1席あたり35万円に過ぎない。しかも、市立とはいえ吹田市は建設費を全く負担していない。民間団体で建設して、吹田市に寄付された。建設費が抑えられたのは、基礎・柱・梁などをプレキャストコンクリート工法とした事で、工場でパースを作り、現場で組み込んでいくという方式を採用した事にある。この工法を、スポーツコアの改修にも採用したい。この他にも、仙台市「ユアテックスタジアム(仙台スタジアム)〜建設費130億円」も参考になる。収容人数は、1万9694席と決して大きくはないが、観客が楽しくサッカー観戦が出来るように工夫されているため「劇場型スタジアム」と呼ばれている。特に、どの座席からも試合が見やすくなるようせり上がりスタンドとなっており、すべての観客席には屋根が付いている。交通のアクセスも良く、スタジアムに隣接して地下鉄の駅もある。この他にも参考になるのが、2万4490人収容の佐賀県鳥栖市「鳥栖スタジアム」(建設費97億円)、約2万人収容の千葉市「フクダ電子アリーナ」(建設費81億円)、約1万5千人収容の「北九州スタジアム」(建設費89億円)などで、魅力的なスタジアムとして定評がある。
この高岡スポーツコアの新サッカースタジアムは、基本的には『カターレ富山』の新しいホームスタジアムとしたいが、富山市側の抵抗も想定される。その場合は、高岡市に本拠地を置く富山県第2のJリーグチーム誕生も視野におきたい。高校野球では、富山商業と高岡商業が対戦すると観客も多く詰めかけて、早慶戦のような盛り上がりを見せる。高校サッカーでも、富山第一と高岡第一が対戦すると、やはり多くのサポーターがスタジアムで声援を送る光景がみられる。つまり、富山市のチームと高岡市のチームが対戦するダービーは大変盛り上がるのだ。これを、富山県内のJリーグでも実現できれば、もっとサッカーは盛り上がるだろう。
富山県の規模だと、Jリーグチームはひとつで良いという意見の方もいるが、なぜふたつあったら駄目なのか疑問だ。実際に全国的にも、1県でJリーグチームが2つや3つあるところが存在する。富山県は富山市にひとつあれば良いという意見があるのも、閉鎖的で保守的な土地柄だからとも言えるわけで、これを変えていかない限り、富山県は良くはならないだろう。勿論、チーム運営費には多額の年間予算が必要ではある。J1であれば最低でも年間20億円以上、J2では年間10億円以上、J3では年間5億円以上が必要とされている。現状のカターレ富山でも、年間予算が約10億円程度となっている。
しかし、全国を見てみると、八戸・天童・いわき・鹿嶋・柏・調布・町田・川崎・平塚・相模原・磐田・藤枝・沼津・豊田・松本・亀岡・吹田・東大阪・丸亀・鳴門・今治・鳥栖・北九州・新富(宮崎県)・沖縄など県庁所在地ではない25都市にJリーグチームがある。また、1県に2チームや3チームといった複数のJリーグチームを抱えているところも増えてきた。複数クラブを抱えている自治体としては、福島県・茨城県・埼玉県・神奈川県・千葉県・東京都・静岡県・長野県・大阪府・愛媛県・福岡県と11都道府県にも及ぶ。青森県・栃木県・沖縄県でもJリーグ入りを目指しているチームがあり、今後も増えていくだろう。富山県だけが、県内にJリーグチームが2つあってはイケナイという理由にはならないのだ。地域内差別的な意見は如何なものかと感じる。
富山県にはJリーグ入りを目指しているチーム『富山新庄クラブ』がある。現状は、富山市がホームタウンとなっているが、高岡市に誘致できれば、松本山雅やFC今治のようなチームになる可能性もでてくるだろう。仮に富山市の街なかスタジアムが実現して、カターレ富山のホームスタジアムとなるようであれば、『富山新庄クラブ』を高岡スポーツコアに誘致したいものだ。県内第2のJリーグチームが高岡側に実現できる意義は大きい。このチームは、高岡市だけでなく、県西部のチームとなる必要がある。その為には、チーム名にも工夫を持たせたい。高岡市出身の藤子F不二雄さんの『ドラえもん』と、万葉線のアイトラムなどに使われる『あいの風』ブランドを組み合わせて、チーム名を『アイのもんず高岡』とすることも面白いのではないだろうか。
↓ クリックで拡大表示します
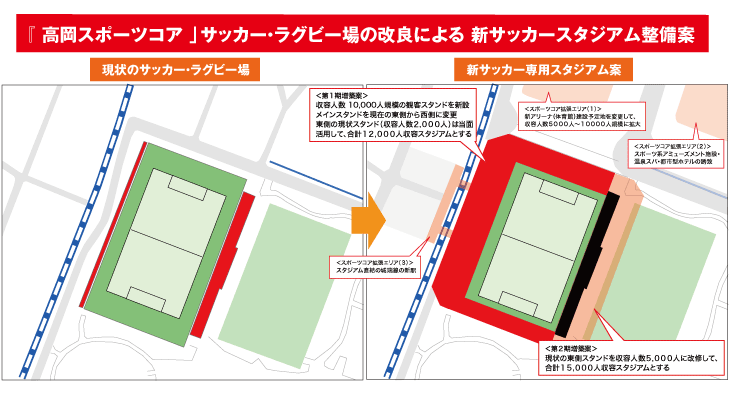
<庄川河川敷にサッカー・ラクビー場を整備>
高岡スポーツコアのサッカー・ラグビー場を、サッカー専用スタジアムにすることで、ラグビー場の扱いを考える必要がある。基本的には、ラグビーの試合を高岡市城光寺陸上競技場で主会場としたい。。ただ、普段のサッカーやラグビーが練習するグランドが、高岡では不足している。
そこで考えたいのが、庄川河川敷の再整備による、サッカー・ラグビー場の確保だ。現在、庄川河川敷は、三好子・蓮花寺にある『高岡庄川緑地運動公園』と、『牧野河川公園多目的広場』がある。高岡庄川緑地運動公園には、野球場、サッカー場、テニス場、ゲートボール場、緑地公園などが整備されいる。牧野河川公園多目的広場は、まだ整備途中であるが、野球場や緑地公園などの整備が進んでいる。この2つの河川敷運動公園に再編成を考えたい。現在は、いすれも複数のスポーツ施設整備を行っているため、各種の大会を開くには、会場が分散してしまう。また、極端に野球場が多いのも課題だろう。もっと、日頃から大会などが開催できる施設として、河川敷公園を再配置させたい。
これらの河川敷整備は、所管の国土交通省が行い、施設の運営維持を高岡市が行うことになる。高岡市にとっては、財政面の負担がなく行える点は、非常に意義がある取り組みとなるはずだ。
(高岡庄川緑地運動公園)
・サッカー・ラグビー場 4面確保
・テニス場 場所を移設して6コート化
・パークゴルフ場は現状のまま
・野球場は牧野河川公園に移転させて集約させる
・堤防の斜面を階段状のコンプリート護岸に整備して、観客席として活用できるようにする
・照明施設も設置して、夜間での使用や防災拠点としても使用もできるようにする
(牧野河川公園多目的広場)
・野球場 4面確保
・堤防の斜面を階段状のコンプリート護岸に整備して、観客席として活用できるようにする
・照明施設も設置して、夜間での使用や防災拠点としても使用もできるようにする
( 新設上伏間河川公園)
・新たにイオンモール高岡に近い上伏間の河川敷を緑地公園化
・照明高岡庄川緑地運動公園や牧野河川公園多目的広場を補完する公園と位置付ける
<WEリーグの女子サッカーチームの実現>
Jリーグのホーム戦は、年間19試合しかない。カップ戦を加えても、22〜25試合程度だろう。高岡スポーツコアの新サッカースタジアムの稼働率を高めるには、女子プロサッカー『WEリーグ』チームの実現の重要な課題となる。まだ、WEリーグのチーム数が少ないが、いずれはJリーグと遜色ないレベルに高まっていくと考えられる。JリーグとWEリーグの試合数を合わせて、年間40〜50試合程度になれば、プロ野球リーグのスタジアム稼働率と遜色のないレベルとなる。そうなれば、スタジアムの民間運営も可能性が高まるだろう。
↓ 松本市にあるJ1基準スタジアムのアルウィンは、露天掘り方式で造られている
|
 |
 |
|
|
|
|
【試合観戦を楽しめるサッカースタジアムとは〜その特徴まとめ 】
1、フィールド(ピッチ)から観客スタンドは、できるだけ近づける
2、観客席の最前列は、フィールド(ピッチ)と同じ高さまで低くする
3、観客スタンドは、見やすいよう競り上がりを急にする
4、収容人数は、3万5千人収容規模が理想(ワールドカップ対応)
5、メインスタンドは西側に配置、最前列までカバーする大屋根を設置する
6、露天掘りのスタジアムとし、将来のドーム化も可能にしておく
7、電光掲示板と大型ビジョンの充実
8、メインとバックスタンドは、一人掛けの独立シートとして、座席幅を確保、
座席方向をピッチ中央に向ける
9、メインとバックスタンドは、背もたれ・肘掛け・ボトルフォルダーを付ける
10、特別観覧席・プレス席の確保
11、ナイター設備は塔体方式ではなくて帯型方式とし、照度は1500〜2000ルクス
12、鉄道駅やショッピングセンターなどを併設したボールパーク化
↓ユナイテッドスタジアム仙台 |
|
|


|
|

<検討したい項目>
・B1リーグ仕様の5千人超収容規模のアリーナ確保
・高岡スポーツコアの新体育館をB1リーグ仕様に
|
<高岡スポーツコアの新体育館を、『B1リーグ仕様』アリーナに>
Bリーグの『富山グラウジーズ』 は、富山県初のプロスポーツチーム。特に、冬が長い富山にとっては、冬場に楽しめるプロスポーツとして重要な役割がある。現在のホームアリーナは、4千6百人収容の富山市総合体育館(建設費100億円)。しかし、Bリーグが求める1部リーグのホームアリーナは、5千人以上の収容能力で、若干足りていない。新しいB1リーグでは、このアリーナ確保が必須となる。富山市では、富山市総合体育館を改修して観客席を5千人以上とするという。しかし、座席数を増やすために、座席の間隔を狭くするなど、観戦環境は悪化することが予想される。富山県では2万人規模のスタジアムや1万人規模のアリーナ実現を検討したが、結局は3千人収容の武道館となった。5千人を超えるアリーナの実現は遠ざかっている。
そこで検討したいのが、高岡市で計画されている新体育館を、観戦が楽しいB1仕様のアリーナとすることだ。現在計画されている高岡市の新体育館は、観客席が3千人収容となっており、今後は5千人以上の設計変更が必要となる。幸いにも、高岡市の財政難から新体育館の着工が凍結されており、計画を見直すことが可能だろう。更に、富山市側はすでに多くの体育館があり、これ以上の新アリーナ建設は無理がある。高岡スポーツコアであれば、新高岡駅に近く、JR城端線も隣接していることから、交通アクセスは整っている。
まずは、高岡市の新体育館計画を、富山県初の1万人収容アリーナに規模を拡大したい。高岡市には、現在の市民体育館と同規模の竹平記念体育館があることから、高岡の新アリーナではコンサートや演劇なども行なえるように音響設備も充実させ、固定席を基本とした密閉型の円形アリーナとして整備したい。マディソン・スクエア・ガーデンや横浜アリーナなどを参考に、Bリーグ・Vリーグの試合観戦やコンサート・演劇といったエンターテイメントを楽しめるアリーナとしたい。新幹線駅前に1万人収容のアリーナができれば、広域からの集客が期待できる。当然、採算性も高くなり、『民設民営』での実現も可能性が高まるだろう。
建設場所も見直したい。現在の計画場所は新高岡駅からは離れた場所がネックだろう。新高岡駅と高岡スポーツコアの間には、開発可能なエリアがある。このエリアをスポーツコアの拡張エリアにしたい。そして、イオンモール高岡に隣接したカタチで、新しいアリーナを設置できれば、新高岡駅を出た真正面にアリーナを望むことができ、インパクトが非常にある。実現すれば、新高岡駅の周辺は魅力的なエリアに変貌できるだろう。
鯖江市にあるサンドーム福井(建設費164億円〜管理棟を含む)は、最大1万人収容可能の本格的な円形アリーナ。スポーツの国際大会をはじめ、ジャニーズ系などのコンサートも開催されるなど存在感が高い。さらに福井市では、新幹線開業にあわせて、5千人収容の新アリーナを福井駅周辺に整備する。Bリーグ参入を目指す地元チームのホームアリーナとして使用するほか、コンサート誘致を行うという。新幹線駅周辺ということで、広域からの誘客に活かす計画だ。福井市が主体で建設するが、福井県も建設費負担で支援するという。
新潟県長岡市では、B1リーグの『アルビレックス新潟BB』がホームアリーナとする『アオーレ長岡』がある。アリーナの収容人数は5千人とB1仕様をクリアしている。市役所を併設した施設で、設計は隈研吾氏が手がけ、総事業費は120億円といわれる。
石川県でも金沢市に、総工費は93億円をかけて、B1リーグに使用できる最大5千人収容可能な『いしかわ総合スポーツセンター』が整備された。また、地元の北國銀行では、小松市に最大1万人収容可能なアリーナを建設する予定になっている。
隣県都市と比較すると、富山県があきらかに立ち遅れている。これに対しての危機感が、県内関係者から聞かれないのは、あまりにも残念だ。
<高岡スポーツコアは一括で『民設民営(PFI方式)』の導入を!>
高岡スポーツコアの新サッカースタジアムと合わせて、新アリーナを整備できれば、プロスポーツのメッカと位置付けることができる。この実現には、新サッカースタジアムと新アリーナを含めて、『民設民営(PFI方式)』を導入することも検討したい。
ジャパネットグループの『長崎スタジアムシティプロジェクト』では、2万人収容のJ1仕様サッカースタジアム、6千人収容のB1仕様アリーナに、ショッピングモール、オフィスビル、ホテルを、800億円の巨費を投じて民間主導で開発している。
先行事例を参考に、できれば高岡スポーツコアを全体一括で、『民設民営(PFI方式)』の導入を図りたいものだ。高岡スポーツコア近くには、北陸最大規模のイオンモール高岡と連携することを想定すれば、イオンに事業主体をお願いするのが、もっとも実現への可能性は高まると考える。『イオンスポーツコア高岡』として、一体的に整備できれば、県庁所在地ではない高岡市であっても、プロスポーツのメッカにすることも可能だろう。
J1リーグでサッカーチームを運営する場合には、年間で最低20億円の売り上げが必要といわれている。また、B1リーグのバスケットチームでは、年間12億円以上の売り上げが必須とされており、下回るとB2に降格されるという厳しい条件もある。高岡スポーツコアでプロスポーツを成功させるには、大手スポンサーの確保が必須だ。それだけに、イオンやJR西日本の協力をどれだけ受けられるかが鍵と言える。そういった意味では、『長崎スタジアムシティプロジェクト』が参考になると同時に、ライバルにしたいものだ。そして、チームの運営を大手企業に担ってもらうことも検討する時期ではないだろうか。イオンに直接運営してもらったり、あるいはエンターテイメント系の企業に運営を売却することも考えられる。B1の島根をバンダイナムコが買収したように、富山県にゆかりのある『KADOKAWA』も運営を担ってもらう候補になれば面白くなるだろう。
|

|
  |
↑鯖江市のサンドーム福井 (1万人収容アリーナ) ↑ アオーレ長岡 (5千人収容アリーナ)

<検討したい項目>
・NPB(日本野球機構)のプロ野球球団誘致
・ボールパーク高岡の改修
・開閉屋根付きスタジアム(3万人収容)実現
↓開閉屋根を備えた福岡PayPayドーム ↓野球観戦が楽しいマツダスタジアム |
 
|
 |
↑クリックで拡大表示します
<NPB(日本野球機構)のプロ野球球団誘致>
富山県に、NPB(日本野球機構)の本格的なプロ野球チームが実現できれば、全国区の地域として大きなアドバンテージを持つことができる。この実現には、大きなハードルはあるが、まったく不可能ということはない。実現するには、ふたつのケースが想定される。ひとつ目は、現在のNPB(日本野球機構)加盟チームを誘致する。ふたつ目は、NPB加盟チーム数を増やすこと。現在の12チームから16チームに増やそうという機運もある。
富山県でNPBチームを実現させるには、富山県単独では厳しいのは確かだが、ホームタウンの立地条件で可能性が出てくると考える。その鍵を握るのは、北海道北広島市に誕生した新球場『HOKKAIDO BALLPARK』だ。北海道日本ハムファイターズの新しいホームスタジアムは、札幌市からは20キロ以上離れた場所に建設された。札幌駅ー北広島駅間は、約24キロある。しかも、北広島市は道庁所在地ではない人口5万人あまりの都市になる。チーム名も札幌の都市名ではなく、北海道を名乗っているのも重要な点といえるだろう。広いエリアを対象としたチーム名は、他にも東北楽天イーグルスがある。
富山県でNPBチームを実現させるには、北陸を名乗ったチーム名と、ホームスタジアムを富山市や金沢市ではない、第3都市に『北陸ボールパーク』を設けることがポイントになると考える。富山市と金沢市の距離は直線で約52キロ、富山駅と金沢駅の在来線では約59キロほど。この2都市の間にある、射水市・高岡市・砺波市・小矢部市・津幡町・かほく市・内灘町の人口を加えると、富山市から金沢市までのエリア『北陸メガロポリス』には、人口140万人が住んでいる。これだけの人口規模であれば、十分にNPBチームのフランチャイズとなれるだろう。
プロ野球の球団運営には、年間で最低でも40億円は掛かると言われている。企業の広告塔的な役割があるとはいえ、ある程度の観客動員による収入が必要ともいえる。年間120万人の観客動員が確保できれば、他の地域の球団と遜色がなくなる。週末や休日の観客動員が2万5千人、平日ナイターが1万5千人となれば、年間120万人の目標に手がとどく。『北陸メガロポリス』であれば実現可能だと考える。
(大手資本による球団実現を)
北陸を冠とするNPBチームの実現には、既存のNPBチーム誘致がまず考えられる。例えば、ヤクルトスワローズを誘致して、『北陸ヤクルトスワローズ』として実現させる方法。
また、NPB加盟チーム数が増えることを想定して、現在のプロ野球独立リーグチーム『富山サンダーバーズ』と『石川ミリオンスターズ』を合併した、『北陸〇〇(企業名)サンダーバーズ』を創設する方法も考えられる。いずれにしても、両県の県庁所在地ではない場所がホームスタジアムにしないと、両県民が地元のチームという意識を持たないだろう。
また、NPBチームの実現には、大手資本のオーナーチームとする必要がある。現在もNPB加盟チームは、大手企業が運営を担っている。そのためには、大手資本の誘致は欠かせないだろう。今後、プロ野球チームを運営できそうな企業となると限られてくる。想定される企業で最有力なのは、サイバーエージェントだろう。Jリーグの町田を買収後、J2からJ1に昇格させて優勝争いまでできるほどのチームに育て上げている。ネット動画配信のAMEBAを抱えており、スポーツのコンテンツとしても、今後はプロ野球も視野に入ってくるのではないだろうか。そのほかにも、B1リーグの島根を持っているバンダイナムコや、外資系ではJリーグの大宮を買収したレッドブルに中国のBYDなども可能性があると考える。
【北陸NPBチームの北陸ボールパーク候補地『小矢部市の石動駅隣接地』】
北海道北広島市の『 HOKKAIDO BALLPARK』をモデルに、北陸でNPBチームの『北陸ボールパーク』を実現できる可能性がある場所を考えると、もっともベストな場所が、小矢部市の石動駅周辺ではないだろうか。富山県と石川県の県境にある都市であり、この場所であれば両県民が、『地元のNPBチームだ』という意識を持ってもらえると考える。
石動駅は、金沢駅からだと在来線で24.6キロと、ほぼ札幌駅ー北広島駅の距離感と一致する、また、高岡駅からは16キロと近い。ただ、富山駅からは34.8キロと距離がある。この課題を解決するために、石動駅近くを走る北陸新幹線に、新駅『新石動駅』を設けることも考えたい。かつて、小矢部市では新幹線駅設置を目指したこともあったが、金沢や新高岡に近いということで実現しなかった。しかし、金沢-新高岡間が39.7キロに対して、小松-加賀温泉間が14.5キロ、加賀温泉-芦原温泉間が15.4キロ、芦原温泉-福井間が18.0キロ、福井-越前たけふ間が19.0キロと駅間隔が極めて近い。仮に、金沢 -新高岡駅間に新石動駅を設けたとしても、新高岡-新石動駅間が16キロ程度、新石動-金沢間が24キロ程度あり、小松-越前たけふ間にある駅間隔と比較しても、十分な駅間距離が確保できていると言える。石動にNPBチームのホームスタジアムができれば、新幹線駅の実現に向けた条件が整ってくる。新幹線の新駅『新石動駅』が実現すれば、富山駅からはわずか15分、金沢駅からは9分で結ばれる。
鉄道を利用してスタジアムを訪れる観客は、『HOKKAIDO BALLPARK』の場合で13,500人と想定されているが、これを北陸にもあてはめて考えた場合、現状の在来線輸送力では対応できない可能性が高い。そこで、石動駅の改良が必要となる。現在、石動駅は3つのホームがあるが、引き込み線などを改良すれば、ホームを5つにするも可能だ。実現できれば、石動駅始発・終着の野球観戦用臨時列車を運行できるようになる。また、北陸新幹線の輸送力を加えれば、十分な輸送力を確保できるだろう。しかも新幹線であれば、富山駅以東の新潟県や金沢駅以西の福井県からの誘客も見えてくる。
石動駅での新しい球場『北陸ボールパーク』のイメージは、規模や内容もできるだけ『HOKKAIDO BALLPARK』に近いもので想定したい。
『HOKKAIDO BALLPARK』は、コンセプトが、国際競争力を有するライブ・エンターテイメントとしての『世界がまだ見ぬボールパーク』。開閉式屋根と天然芝フィールドを備えた、約3万5千人収容の新スタジアムは、JR線の駅に直結する。建設費は600億円といわれ、温泉スパやバーベキューをしながら試合を観戦できるほか、ショッピングやオープンカフェなど日頃から楽しめるボールパークとなっている。しかも、この球場の素晴らしい点は、球場のデザイン設計を米国テキサスの企業「HKS」が行った事だろう。レンジャーズやホワイトホックスなどの大リーグ球場を多数手掛けており、新球場はアジア最高のボールパークとなるはずだ。
『北陸ボールパーク』でも、3万人〜3万5千人収容規模の観客席と、全面天然芝フィールドに開閉屋根を確保したい。開閉屋根は、設置スペースの制約や建設費を抑える為にも、蛇腹式の薄膜屋根として、天候不良時のみ屋根を閉じる方式とする。あと、検討したいのは石動駅および新幹線新駅と一体になったスタジアムにすることだろう。両駅から徒歩1分程度で、雨にも濡れずにスタジアムへ行ける構造とできれば、日本海側屈指の観光スポーツ都市になる。
『北陸ボールパーク』の運営は、誘致する球団に運営を委ねる『上下分離方式』、もしくは『民設民営(PFI)方式』を採用したい。例えば、『 HOKKAIDO BALLPARK』は、球団の日本ハムファイターズが自社で建設した。『東京ドーム』では、球団が東京読売巨人軍、ドーム自体の運営は三井不動産が中心に行なっている。『北陸ボールパーク』でも、同様に大手資本による運営や球団が自ら運営することを目指したい。実現すれば、自治体の負担は少なく済むからだ。
また、スタジアムに隣接してショッピングモールを設ける必要もある。小矢部には、観光施設とも言うべき『三井アウトレットパーク北陸小矢部』がある。この三井アウトレットパークと親和性が高いショッピングモールを想定したい。例えば、三井系のショッピングモール『ららぽーと』が考えられる。場合によっては、スタジアム併設ショッピングモールを『三井アウトレットパーク』に、既存の『アウトレットパーク北陸小矢部』を『ららぽーと』に転換することも考えられる。
課題となるのは、車を利用してくる観客対応。スタジアムへ訪れる観客のおよそ半数近く(約1万7千人)は車やバスでの来場が想定される。『HOKKAIDO BALLPARK』では、4,000台の駐車場が設けられているが、『北陸ボールパーク』では2,000台程度の駐車場確保を考えたい。スタジアムにショッピングモールを併設することで、日頃から使える駐車場とする。また、『三井アウトレットパーク北陸小矢部』には、2,800台の駐車場があり、スタジアムとアウトレットパークを結ぶBRTやBHLSを整備することで、車利用者を分散させることも考えたい。
スタジアムに向かう道路整備も課題となる。小矢部市には、北陸道と能越道の高速道路に、国道8号線といった幹線道路が環状的に整備済みではある。ただ、問題なのは、それぞれの道路から石動駅へ向かうアクセス道路が脆弱である点だろう。北陸道小矢部インター、能越道小矢部東インター、8号線安楽寺インターの3インターからスタジアムを結ぶ地域高規格級の道路整備は欠かせないと考える。
↓エスコンフィールド『HOKKAIDO BALLPARK』 |
 |
 |
↑クリックで拡大表示します
【北陸NPBチームのファームパーク候補地『ボールパーク高岡の活用』】
北陸NPBチームの誘致で課題となるのは、ファーム球場の確保だ。北海道日本ハムファイターズでは、ファームパークの構想がある。ホームスタジアムとは別にファームのボールパークというイメージだ。北陸NPBチームでも、同様のファームパーク実現を目指したい。その候補地として考えたいのが、『ボールパーク高岡』の活用だ。『ボールパーク高岡』は、あいの風とやま鉄道の直ぐ側にあるという好立地な場所に建設されており、球場の横に新駅を設置できれば、金沢駅ーボールパーク高岡新駅間が34キロほど、富山駅ーボールパーク高岡新駅間が25キロほどで結ばれる。埼玉西武ライオンズの『ベルーナドーム』に隣接した西武球場駅と新宿駅間は36キロほどと比較しても、成功する可能性がある立地といえる。あいの風とやま鉄道やIRいしかわ鉄道は、駅数がきわめて少ないことから、金沢駅からだと約28分、富山駅からだと約20分で球場にやってくることができる。
また、『ボールパーク高岡』の魅力は、球場のすぐ傍を能越自動車道が走っている点だろう。能登や砺波からのアクセスも良く、富山県と石川県を足した人口210万人エリアの中心に『ボールパーク高岡』が位置することになる。
『ボールパーク高岡』(総工費49億円)のファームパーク化では、米国的な『ボールパーク』のように、スタジアムに隣接して、大型ショッピングセンター・遊園地・ホテル・マンションなどを併設して、野球の試合が開催されない日でも、多くのお客さんで賑わう場所としたい。また、スタジアム自体も、ホームスタジアムと同様に改修する必要もある。
現在、富山県内でプロ野球が開催できるスタジアムは、アルペンスタジアムしかない。3万人収容するアルペンスタジアムの建設費は57億円ほど。一方、『ボールパーク高岡』も総工費49億円を掛けたが、1万人収容に留まっている。また『ボールパーク高岡』の内野は黒土仕様。これは、高校の野球球児に夢をいうことで甲子園仕様にしたということだが、時代はプロ野球選手や大リーグ選手を夢みる時代だろう。更に、富山県内では高校野球の為にということで、既にたくさんの甲子園球場的な野球場が造られてきた。砺波市民球場、黒部宮野野球場、魚津桃山野球場がそうであるように、富山県営野球場や高岡市城光寺球場を含めると、5球場が甲子園仕様となっている。甲子園球場的な野球場がこれだけあるのに、新たに増やす必要性があったのかと疑問に感じる。新潟県立野球場「HARD OFF ECOスタジアム」(建設費84億円、3万人収容・将来のドーム設置も可能)は、NPBの球団誘致を想定したスタジアムとなっており、将来的にはドーム球場とすることも可能だという。北陸NPBチームのホームスタジアムでは、本格的な大リーグ仕様を期待したい。
【 試合観戦を楽しめるベースボールスタジアムとは〜その特徴まとめ 】
1、バックネット裏やベンチ側の内野席は、ピッチャーと同じ目線で見れるようできるだけ
最前列席は低く下げる
2、外野ファールゾーンの観客スタンドはフィールド近くまで迫るようなフィールドシートを確保
3、ベンチ横の内野席に、砂被りスタンドを設ける
4、観客スタンドは、見やすいよう競り上がりを急にする
5、内野席は、十分な幅を確保して独立した独り掛けシートとして座席の方向をマウンドへ向ける
6、内野席には、背もたれ・肘掛け・ボトルフォルダーを付ける
7、観客席(内野席は必須)には、屋根を設置する
8、外野・内野のフィールドは、天然芝とする
9、ブルペンは、内野観客スタンド地下または3塁側(相手方ベンチ側)の外野スタンド側に設置
10、本塁からバックスクリーンへ向かう方角を、東北東にする
11、両翼100メートルとセンター125メートルの確保
12、1塁側(ホームベンチ側)に観客席を増やし、左右非対称型観客スタンドとする
13、ナイター設備は塔体方式ではなくて帯型方式を採用して、照度は内野3000ルクス・
外野1500ルクス
14、スコアボードの充実(電光掲示・選手表示・大型ビジョン)
15、100年使えるスタジアムデザインとする
16、収容人数は、3万〜4万人規模を確保
17、露天掘りのスタジアムとし、将来のドーム化も可能にしておく
18、鉄道駅やショッピングセンターなどを併設したボールパーク化。
|

|
  |
<富山の女子プロスポーツ育成を!>
富山では、これでプロスポーツチームが、バスケットボール・野球・サッカーと3チームに充実してきた。しかし、いずれも男子スポーツとなっている。これからは、女子スポーツの充実を必要だ。特に、女子Vリーグ所属している「黒部アクアフェアリーズ」を大きく育てる必要があるだろう。特に重要な点は、ホームが県都富山市ではなくて黒部市に置いている事だ。また、女子チームとしては、日本ハンドボールリーグ(JHL)に加入した、『プレステージ・インターナショナル アランマーレ』の存在も大切だ。こちらも、ホームは射水市で、富山市ではない。これら、「地域球団」として頑張っているチームの存在は、小さな都市でもプロチームが成り立つ可能性を示している。これまでの「なんでもかんでも、富山市でないと無理だ」という富山県独特の固定概念を打ち破れる事を期待したい。また課題なのは、女子サッカーチームが、現状無いことだ。早期に、カターレの女子チーム誕生を期待したい。女性が、富山県でも活躍できる。そんな環境や雰囲気づくりは、富山県の超保守的なイメージ脱却に繋げられるだけに、とても重要な課題だろう。
<プロチームの運営強化>
保守的だった富山県で、プロスポーツチームが増えていることは、大きな変革となる。新たに男子プロハンドボールリーグの参入を目指して、氷見市には『富山ドリームズ』も誕生した。一方で、プロチームの運営には、多額の財源が必要となっている。県内のチームはいずれも財政的に厳しい状況が続いている。県民チームとして育てる為には、もっと横の連携が必要と考える。新潟アルビレックスのように、県内のプロチームの名称を統一して、チームカラーも同じにする事で、県民意識を一体化させた好例も参考にすべきだろう。富山県のプロチームがひとつの名称、そしてひとつの組織に集積化させ、新しい形の県民プロチームとして、運営の完全一体化も有効な手段ではないだろうか。現状の各チームは、資本形態が異なることから難しい面もあるが、是非検討してもらいたいものだ。
また、サポーター・ブースターの会員を増やす工夫も欲しいものだ。その為に県がメインとなって、県内のプロチーム共同の会員カード(クレジット機能・県内交通機関共通IC機能付き)を設けることで、年会費の安定的な確保を図ることも重要だと考える。
富山のスポーツをいかにして盛り上げて行くかという点も重要である。そのためには、富山県民がもっとこれらのスポーツを目にする機会が増えてこないといけないだろう。
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|