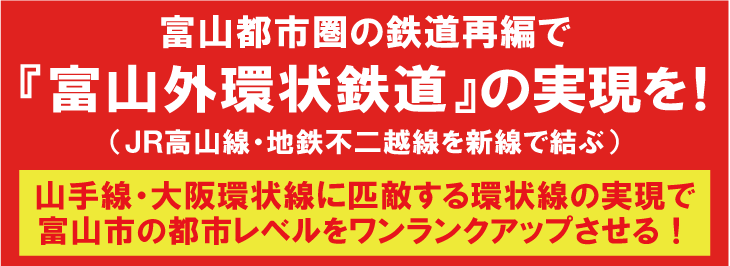 |
|
<富山市都市圏内に『富山外環状線』を整備>
富山市では、鉄道を軸に据えて「環境問題」や「高齢化時代」に対応した街づくりを進めている。この政策を更に進めて、富山市都市圏内で外郭の環状鉄道実現を目指したい。地鉄上滝線(富山ー南富山間)と、現在のJR高山線(富山ー速星間)の電化。富山南ー富山空港ー速星間を新線で整備して、富山市都市圏内の環状鉄道「富山外環状線」を実現させたい。
この富山外環状線は1周22キロ程で、JR大阪環状線とほぼ同規模となる。1周約40分、運行間隔は上下線とも日中は10分〜15分、ラッシュ時は7〜8分間隔を確保したい。
新線は、富山空港への乗り入れやアピタ富山インター店などの大型商業施設、北陸道富山インターチェンジなどをルートとして検討したい。新線区間は複線化とし、富山南ー富山インター間は連続立体高架化、富山インターー速星間は盛り土高架化(一部トンネル化)とし、開通後は、富山ー富山南間を複線の連続立体高架化を検討する。また、富山駅-稲荷駅間で、かつてあった地鉄と北陸線の渡り線を復活する必要がある。その際には、県道八幡田稲荷線の地下化と渡り線の立体交差化など北陸新幹線の2層高架を含めると、4層の立体交差をする事も必要だろう。
高山線からは特急「ひだ」を、外環状線に直接乗り入れて富山空港経由とすることで、空港から飛騨観光地を直結させる。また外環状線を活用して、富山空港と高岡方面を結ぶ運行車両も検討したい。この外環状線化にあわせて、富山地鉄上滝線の南富山ー岩峅寺間を路面電車化して市内軌道線と直結させる。更に市内軌道線を、五福からJR高山線の新駅(安養坊付近)に乗り入れ、利便性を高めさせる。
欧州では、中世時代に街づくりを城(ブルグ)を中心に城壁内へ集約させてきた。城壁を境に、外と中では商業と農業が機能的に分けられた事で、街の機能は文化的にも高いものとなった。欧州では、その思考を現代にも受け継がれている。富山の街づくりも、この外環状線を城壁に見立てて、外環状線内に街機能を集約させることで、都市としての魅力を高める事を目指すべきだろう。このレールブルグ(外環状線内)では、車の走行規制を行い、人を中心とした街づくりを行ないたい。
↓クリックで拡大表示します |
|
 |
 |
<『BHLS(バス・ハイレベル・サービス)の導入を!>
富山外環状線が実現できれば、外環状線の内側にさらになる2次交通を確保する必要がある。しかし、鉄軌道のLRT整備にはそれなりの建設費用が掛かるため、ある程度の利用者見込みがなければ導入しずらい課題がある。そこで、国内ではLRT的なバス高速輸送システム『BRT(バス・ラビット・トランジット=バス高速輸送システム)』の導入を進めている自治体が増えてきた。理由は、導入費の安さだ。一般道を活用できて、車両も一般的な路線バスではじめられる。しかし、BRTは定時運行性や速達性に乏しく、モビリティデザイン的にもバスというイメージを脱却できていない。名称はBRTという新しいイメージはあるが、いざ導入すると、これまでの路線バスとの違いを感じられないケースが多い。
先行する欧州では、このBRTが抱える課題を改善させた『BHLS(バス・ハイレベル・サービス)』が登場しはじめている。これは、BHLSの専用道路を整備させたことで、定時運行性を確保し、高速運転で速達性を高め、2連結から4連結バスによる大量輸送を可能にしたものだ。
また名古屋市では、BHLSに近い構想の『SRT(スマート・ロードウェイ・トランジット)』を、中央リニア新幹線開業時までに導入する計画を進めている。これは、LRTのような乗り心地の車両開発とBRTのような道路網を活用するイメージと言われ、既存鉄道や地下鉄を補完して都市の回遊性を高めることが目的とされている。
SRTのモデルとなったのが、フランス『ルーアン市』のTEORだ。TEORは、一般的なBRT(専用バスレーン)を進化させて、一般道路からバスレーンを完全分離させた専用路線化したバスシステム。LRTに匹敵する定時制と輸送力を実現させている。また既存のLRTは、市街地で地下鉄化させるなど、高い公共交通網を構築している。
BHLSによって、富山外環状線の内側に2次交通ができることになる。BHLSの実現は、LRTと並んで象徴的な街づくりとすることができるだろう。山手線や大阪環状線の内側は、地下鉄ネットワークが整備されたことで、2次交通の利便性は高く山手線や大阪環状線の利用者を確保する効果がある。富山外環状線を実現させるためにも、富山外環状線内側の2次交通『BHLS専用道路ネットワーク』を整備する意義は高い。つまり、東京・大阪の環状線内の地下鉄網が、富山市ではLRTとBHLSのネットワークで同じような役割を持たせるのだ。これによって、富山外環状線の内側では、公共交通機関だけで都会的な生活できる環境が可能となる。『富山市なら、東京や大阪と同じ生活ができる』イメージづくりは、とても重要となる。
BHLSで導入する車両は、日本初となる3連結バスの完全な自動運転車両としたい。バス運転手の不足が深刻な状況で、改善は難しい状況だ。新設のBHLS専用道路の整備と、既存4車線道路の2車線をBHLS専用レーン転用を組み合わせる。自動運転車両の導入を図かりたい。バス運転手の不足が深刻な状況で、改善は難しい状況だ。『BHLS専用道路ネットワーク』を、全国初の完全自動運転路線として実現できれば、全国に与えるインパクトは極めて大きいだろう。専用道路・専用レーンはカラー舗装を行い、一般道と視覚でわかるようにすると同時に、BHLSの車両は、このカラー舗装に沿って自動運転を行う。また、BHLS路線では、無散水式融雪装置を完備させて、積雪時にも強い路線としたい。
料金支払いシステムは、各停留所に改札ゲートを設けて、バスの車外で支払いする事で、BHLSの定時運行を高めさせたい。車外支払いは、LRTでも導入を検討したい。料金は一律として、利便性を優先させる。運行間隔は、日中は10〜15分間隔、ラッシュ時は7〜8分間隔を目指す。
|
  |
| |
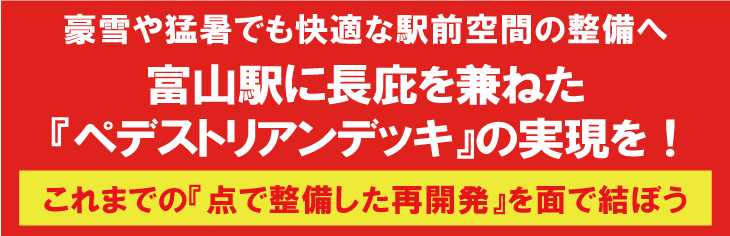 |
<富山駅に長庇を兼ねた『ペデストリアンデッキ』の実現を!>
新幹線で富山駅に降りる訪問客は、富山駅周辺で過ごす駅滞在時間は極めて短い。およそ30分から最大1時間半ほどだ。一方、金沢駅では、駅周辺が目的地化されており、想定される駅滞在時間は、1時間から最大4時間程度だ。富山駅周辺でも、滞在時間をいかに延ばすかが、これからの課題と言える。
その中で特に問題なのは、富山駅の『人動線の悪いさ』だ。駅周辺の施設へスムーズに移動できない、あるいは距離があるという致命的なネックが『人の回遊性』を生まずに、駅なかや駅前の賑わいを損ねている原因となっている。その為、駅前の商業施設は空きテナントが目立っている。
この改善として考えたいのは、駅前の各ビルを2〜3階で結ぶペデストリアンデッキの設置だ。富山駅を軸に、駅前周辺をコリドー型に取り囲むペデストリアンデッキができることによって、人々を駅前道路を挟んだCIC側にも向かわせる事が可能となるだろう。このペデストリアンデッキは、長庇の役割を兼ねたい。ペデストリアンデッキの下も歩道とすることで、雨や雪の日でも、快適に移動できる環境を構築する。猛暑の夏でも、日除の空間としても活用できるだろう。ペデストリアンデッキで結ばれるビルでは、2〜3階に出入口を儲けることで、富山駅前に多重空間を造りたい。商業ビルは上層階への顧客誘導が課題な為、多層階で出入りができる多重空間の実現は、『人動線の改善』や『人の回遊性に繋げる』こととなり、その意義は大きいと言える。
<富山駅直結の『商業ゾーン』実現を!>
富山駅前には、JR西日本が中心に商業施設の再編が進んでいる。新しく商業施設として『マルートとやま』が開業した。残念ながら売り場面積は4千平米ほどで、かなり狭い商業施設となったため、持続可能の商業施設となるのか心配である。また、JR西日本では『マリエとやま』のリニューアルも取り組んでいるが、現状は先行きが不透明な状況だ。『マルートとやま』と差別化を図るためにも『マリエとやま』には目玉となるキーテナントを期待したい。たとえば、家電量販店ヨドバシカメラのマルチメディア館を誘致できれば、これまでにない魅力の要素ともなるだろう。さらに、富山市の第2市役所として活用されている『CIC』に関しても、今一度、商業施設として再生できれば富山駅前は魅力的なゾーンとなる可能性がある。できればJR西日本で再生を目指すことも検討すべきと考える。CICの地下1階から3階までを商業ゾーンとして再構成させ、ここにもキーテナントとして、創業者が富山県出身の『マルイ』が誘致できれば、マリエ・マルート・マルシェ・マルイと『4M』エリアとして、魅力的なエリアに生まれ変わることも可能ではないだろうか。
魅力的な都市には、駅直結の百貨店が多い。大都市では、新しい百貨店がほとんど駅直結型だ。札幌の大丸、名古屋の高島屋、京都の伊勢丹、大阪の大丸・阪急・阪神、福岡の阪急。これらの百貨店では、デパ地下が充実している。生活鉄道に直結していることで、日常からデパートを利用する習慣が根付いている。ところが、地方都市では駅直結の百貨店が、極めて少ない。どうしても、地方の百貨店は昔ながらの商店街に立地しているケースが多いからだ。百貨店を目的に、わざわざ足を向ける必要がある。これが車社会となった地方都市では、苦戦する原因となっているのだ。しかし、地方でも主要駅の利用者は、いまでもそれなりにある。
現状は、富山駅に百貨店の実現はハードルが高い。しかし、デパ地下のようなエリアは構築したいものだ。富山駅の北口には、駅直結とできる未開発の空間がある。北口の西側エリアが活用できるだろう。現在はこども向け公園として暫定的な活用をされているが、ここにデパ地下のような施設を設けたい。惣菜・弁当・スイーツ・有名菓子・酒や日本海の幸が一堂に集まる生鮮市場として、日本海側最大級の駅直結型デパ地下的なイメージの施設を実現したい。こおん施設は、欧州型の大規模市場を参考に、金沢の近江町市場に負けない市民が日頃から買物ができるような大衆市場を目指す事ができれば、富山駅を観光駅とする事も不可能ではないと考える。
あと、駅周辺で不足しているアイテムが、コト消費の施設だろう。シネコンやボウリング場などのスポーツ施設などがあれば、富山駅周辺で長時間の滞在を実現できるだろう。駅周辺で人が多くいるという演出が重要だ。
|
 |
 |
↑JR長野駅
|
↑JR博多駅
|
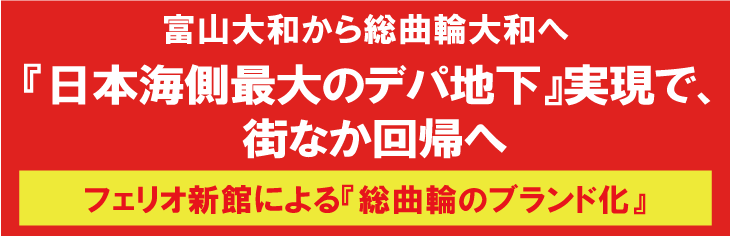 |
<大和百貨店の強化『日本海側最大のデパ地下』実現を!>
県内で唯一の百貨店となった大和富山店。街なかへの回帰を目指すには、大和富山店の強化が急務と考える。その為には、平日から街の賑わいを確保する必要だ。その鍵となるのはデパ地下の強化だろう。そこで考えたいのは、現在の店舗と総曲輪アーケードを挟んだ向かい側にフェリオ新館を設けること。新館の地下を大和のデパ地下拡張エリアにあてるのだ。
参考にしたいのが、浜松市にある『遠鉄百貨店』。かつて浜松市には4つの百貨店があったが、いまや市内唯一の百貨店となっている。遠鉄百貨店は、本館(売場面積2万2千900m2)と歩行者道路を挟んで新館(売場面積1万2千m2)がある。地下階で、本館と新館が繋がっており、大都市の百貨店並のデパ地下が広がっている。平日から高い集客力を誇っており、大和富山店も同様な形態を目指したい。『日本海側最大のデパ地下』が実現できれば、広域からの集客につながるだろう。
フェリオ新館は、地下1階から4階までを売場面積で1万5千m2規模の商業スペースとしたい。デパ地下以外に、ファストファッション系ショップ(GAP・H&M・ユニクロGU・無印良品・ZARA・ハンズ)などを誘致することで、既存の大和ではカバーできなかった若年層の取込を図りたい。また、5階にはコト消費の強化を目指すために、富山県にはまだない『都市型プラネタリウム』も併設したいものだ。上層階にはマンションなどを設けて、採算性の高めたい。
また、大和富山店のブランド力も高める必要がある。金沢の大和本店は、商業地のエリア名を使った『香林坊大和』としているが、富山でも総曲輪のブランド力向上を目指して、名称を『総曲輪大和』に変更することを期待したい。
|
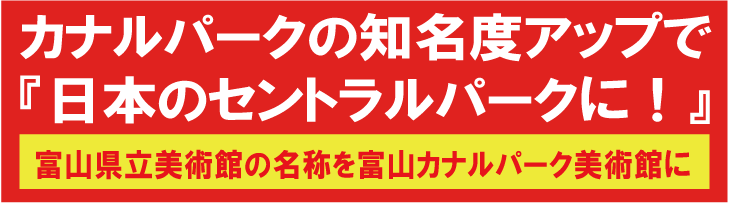 |
<カナルパーク(富岩運河環水公園)を全国区のブランド化>
北陸新幹線で富山駅を訪れる観光客をいかに増やしていくか。その為には、富山市内に観光地を増やす必要がある。全国区のブランド化ができる可能性があるのは、『カナルパーク(富岩運河環水公園)』だろう。一時期、世界でもっとも美しいスターバックスがある公園として、全国での知名度が上がったが、その後はさほど注目されていない。問題なのは、カナルパークという名称の浸透がまだ低い点だ。もっと、カナルパークという名称を、目にする耳に聞くようにする必要がある。そこで、カナルパークの周辺施設を、積極的に名称にカナルパークをつけていく必要性がある。まずは、県の施設で名称変更したい。カナルパークは富山県立美術館があるが、名称自体が富山県立という固い印象で、とてもお洒落感がない。名称からも、どこにあるかわからない。そこで、金沢21世紀美術館の名称にも負けないように、富山県立美術館から名称を『富山カナルパーク美術館』に変更してはどうだろうか。名称からも場所がわかり、印象も柔らかく、訪れたい印象を与えると考える。
また、カナルパークの運河沿いには、開発できるエリアも多い。ここを、文化ゾーンとして、大学、図書館、工芸工房などを整備することで、回遊性を持たせることも必要だろう。普段から、カナルパークを歩く人を増やしていきたいものだ。
運河沿いの道路延伸も重要だろう。現状は、国道8号線の手前で終わっているが、岩瀬まで延伸させることによって、観光ルートにもできると考える。訪れたい場所として、カナルパークを、どう演出するかが大事となる。
|
|
<注意>このホームページは、あくまでプライベートサイトであり、いかなる団体・企業とも関係がございません。
当サイトで使用した画像及びデータの無断転載は禁止いたします。このサイトの主宰は、炭谷壮一(映像作家/街二スト)です。
尚、このページで使用している地図は、AtlasMateを使用しております。複製はご遠慮下さい。
|
|