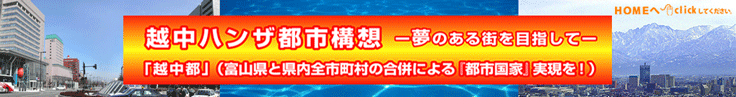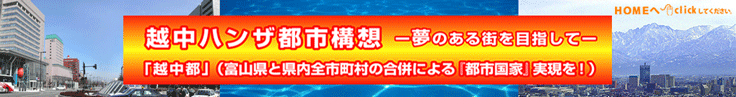<万葉線の新高岡駅へ延伸実現を!>
城端線・氷見線LRT化検討会で議論されたが、事業費(最高435億円)の大きさがネックと言われ、LRT化は難しいという結論となり、新型車両導入がベストという判断が2023年に下された。
これは、極めて残念な判断だ。
城端線・氷見線のLRT化は、持続可能な社会インフラとして『100年先にも鉄路を残すため』の取り組みだったと考える。新型車両導入では、これまでとほとんど変わらず『100年先にも鉄路を残せない』と危惧される。また、新型車両導入は本来ならJR西日本側が取り組むべきことで、公的資金を投入するものではないだろう。
そもそも、城端線と氷見線を一緒にLRT化することに固執したことが残念でならない。
城端線29.9キロと氷見線16.5キロ、あわせると46.4キロもあり、一度にLRT化しようとすれば、それは巨額な投資となるのは必然だろう。まずは現実的な取り組みとして、氷見線のみをLRT化させることが、もっとも意義があることで、氷見線だけであれば1/3以下の投資で済み、取り組みやすい選択肢だったからだ。新型車両導入がベストという安易な結論は、両線の廃線を先延ばしにしただけの結果に終わる可能性が極めて高い。そして大きな問題は、最終的な構想では、新型車両導入とポイントなどの交換などで、総額342億円を投資することになったこと。LRT化する場合の事業費435億円とは、その差がわずか83億円程度に過ぎない点だろう。
宇都宮市では、LRTをゼロから構築してJR宇都宮駅から郊外の工業団地までの14.6キロを2023年に開業させた。総事業費は約684億円にものぼる。当初は反対の声もあったのだが、開業後の利用者は予想を超えたため、大成功の取り組みと言われている。更に宇都宮ライトレールでは、JR宇都宮駅を跨いで都心部へ5キロ程度を延伸される見込みだ。その事業費は、さらに約400億円掛かると見込まれている。今回、事業費が掛かるとして既存鉄道のリニューアルに止まった城端線と氷見線。果たして、宇都宮ライトレールのような大成功例と言われる結果になるのだろうか。
高岡駅と新高岡駅の最大の問題点は、万葉線と氷見線が高岡駅止まりで、新幹線駅の新高岡駅まで直接乗り入れ出来ていないことだ。この問題解決にどう取り組むかを議論する必要があった。しかし、氷見線と万葉線の新高岡駅乗り入れを、別々に議論されている。同じ課題なのに、なぜ別々の話しとなるのか理解できない。城端線・氷見線LRT化検討会の結論では、氷見線を城端線に乗り入れるために、あいの風とやま鉄道(旧北陸線)を平面交差させて実現させることになった。この構想自体は、20年以上も前からあった話しだが、30〜40億円の事業費をかけて平面交差を実現させても、1日あたり氷見線から城端線に乗り入れられるのは、わずか4往復〜最大8往復程度とされている。今後、あいの風とやま鉄道の運行本数が増えれば、平面交差できる本数はさらに減る可能性もある。それだけに、この平面交差方式は意味がないとされてきたが、今回の城端線・氷見線LRT化検討会では、一番良い構想として復活したのが不思議でならない。
現状、城端線と氷見線はリニューアルで決まった以上、次に取り組むべきなのは、万葉線の新高岡駅乗り入れを早く実現させることだろう。万葉線をいかに高岡駅を乗り越えて延伸させるか、早急な対応が必要だ。なぜなら、新高岡駅の利用者増加に伴い、市営駐車場が慢性的な満車状態となってきていることがある。駐車できな車が、周辺のイオンモールなどに駐車するケースが出てきており、イオンモールでは駐車場の夜間閉鎖と時間外まで駐車した場合に高額の駐車料金を課すようになっているからだ。いずれ、新たな市営駐車場整備が求められるだろう。しかし、その駐車場整備に費用をかけるのであれば、万葉線の新高岡駅延伸に費用を回る方が、公共交通の維持に寄与すると考える。万葉線の沿線には、市営高岡駅駐車場や市営御旅屋駐車場があり、既存の駐車場を活用できるメリットも極めて高いと言えるだろう。
<万葉線の新高岡駅乗り入れルート A案『県道58号線ルート』>
(A案)県道58号線にLRT線を整備することで、万葉線を新高岡駅まで延伸させる。
県道58号線を改良して、万葉線のLRT線を整備することで新高岡駅まで延伸させる。あいの風とやま鉄道との立体交差化は、県道58号線の陸橋を、1車線減らしてLRT線を敷設して対応する。将来的には、高岡駅を跨ぐ新設の南北道路を検討する。
<万葉線の新高岡駅乗り入れルート B案『駅南大通りルート』>
(B案 その1)万葉線を高岡駅の2階自由通路に並行して立体交差で駅南に延伸させる。
万葉線を新たに在来線の改札口や自由通路のある2階部分へ高架で乗り入れる。富山銀行本店正面から万葉線を立体化させて、ホテルα1と自由通路にある隙間から橋上駅の改札前まで単線にて乗り入れる。橋上駅では、すれ違いができるようにする。そして、駅南大通りで地上へ降りて、LRT新高岡駅までを駅南大通りのLRT化で結ぶルート案。ドイツのフライブルグ中央駅は、2階に跨線橋でLRTが乗り入れ、1階の国鉄ホームへエスカレーター1本で乗換できるような機能性の高い駅であり、高岡駅でも同じ効果を狙いたい。富山駅が、1階に LRTターミナル、2階に在来線・新幹線ホームなのに対して、高岡駅はその逆、2階に LRTターミナル、1階が在来線ホームとすることで、存在感を持たせることができるだろう。
また、既存のターミナル1階に乗り入れているLRT線は廃止して、代わりにバスターミナルを移設させる。雨や雪に濡れることなく、バスを待つことができるメリットは高い。既存のバスターミナルエリアは、駅前公園として整備させて、イベントなどができるようにする。
B案その1がもっとも理想的なルート案で、あいの風とやま鉄道との乗り換えも便利となる。
(B案 その2)万葉線を駅西側で、あいの風とやま鉄道と立体交差させ、駅南に延伸させる。
現在の氷見線ホーム西側に万葉線が乗り入れて、そこから城端線側に立体交差で渡り線を新設させて接続する方法だ。これは、城端線・氷見線のLRT化を検討された際に、富山県が示した構想を万葉線に置き換えす案になる。単線での立体交差とする。駅南へ立体交差させた万葉線は、高岡駅南口を経て駅南大通りにLRT新線を設けることで新高岡駅まで結ぶルート案。
(B案 その3)万葉線を駅東側で、あいの風とやま鉄道と立体交差させ、駅南に延伸させる。
富山銀行本店の裏通りから万葉線を立体化させ、アパホテルとsorae高岡の間を抜けて、あいの風とやま鉄道を高架で跨いで駅南に抜けます。この区間は単線で整備する。そこから地上に降りて、駅南大通りにLRT新線を設けることで新高岡駅まで結ぶルート案。
いずれの案も、駅南大通りの四車線を二車線に減らして、二車線分をLRT線に転用させます。歩道側をLRT線とすることで、利用者の利便性を高めたい。沿線には瑞龍寺の国宝もあり、観光客の利用を意識した路線とする必要もあるだろう。
(C案)万葉線をあいの風とやま鉄道と立体交差させ駅南で城端線に乗り入れる
富山銀行本店の裏通りから万葉線を立体化させ、アパホテルとsorae高岡の間を抜けて、あいの風とやま鉄道を高架で跨いで駅南に抜ける。この区間は単線で整備する。駅南からは地上に降りて、駅南大通りから県道73号線にLRT新線を設ける。城端線と県道73号線の交差箇所で、万葉線と城端線を接続させる。ここから新高岡駅間を、LRT仕様の600Vで電化して、万葉線の車両を城端線に乗り入れさせる。
万葉線の新高岡駅乗り入れが実現できれば、経済効果は計り知れない。これらの延伸整備にも「開発型鉄路」方式を導入して建設費を賄いたい。新幹線駅周辺に、マンション用地を造成し、その分譲価格に、鉄道整備費を上乗せさせる。また、鉄路整備を目的とした「ホテル税」の導入も考えられる。
これらの収入源と、国からの鉄道整備補助金で早期の実現を目指したい。
<万葉線のフィーダーバスと駐輪場の整備>
万葉線が新高岡駅に延伸できれば、万葉線の利用者が増えるだろう。しかし、課題なのは万葉線からの3次交通網が整備されていない点だ。そこで考えたいのは、万葉線の主要駅からのフィーダーバス実現だ。
・広小路駅を起点に、内免方面を結ぶフィーダーバス
・市民病院前駅を起点に、下田方面と熊野方面を結ぶフィーダーバス
・米島駅を起点に、富山大学高岡キャンパス方面と二上方面を結ぶフィーダーバス
、これらのフィーダーバスが実現できれば、万葉線の利用増に繋がるだろう。バスの運転手不足で既存のバス路線維持が厳しくなっており、路線距離が短いフィーダーバスに資源を振り向けることが意義がある。
また、万葉線のほとんどの駅には駐輪場がない。これも万葉線の利便性を損ねている点と言えるだろう。そこで、市民病院前駅、江尻駅(イオン高岡店前)、米島駅、能町駅に駐輪場を設けたい。万葉線の3次交通が充実できれば、まだまだ利用者を増やすことが可能と考える。
↓クリックで詳細表示します |